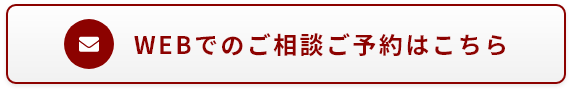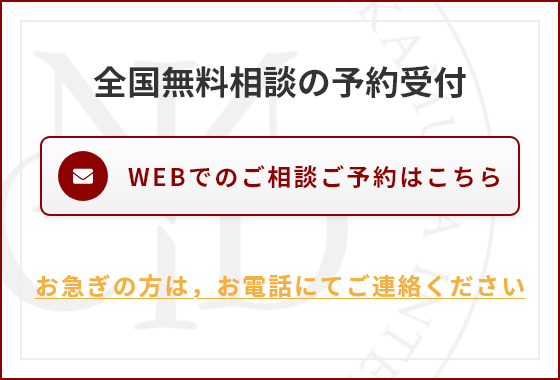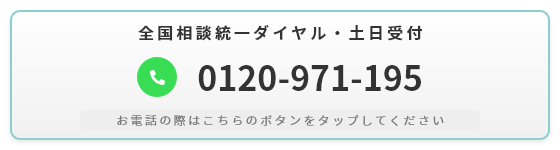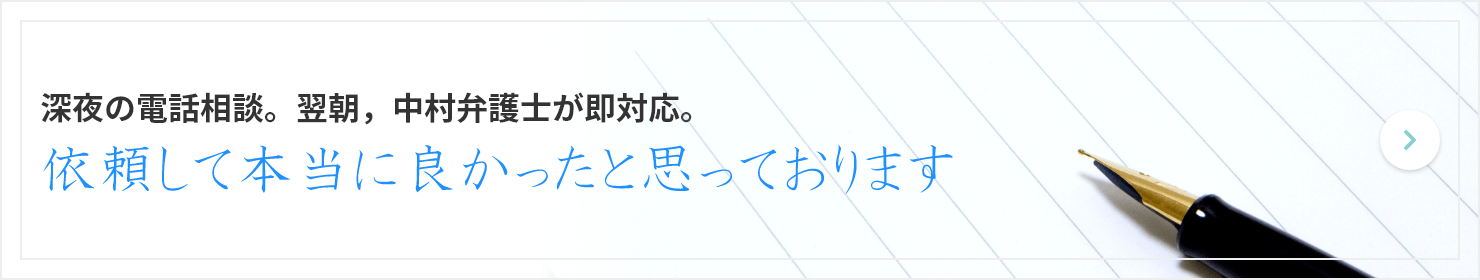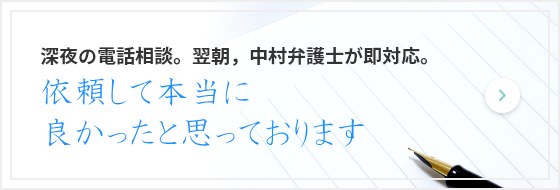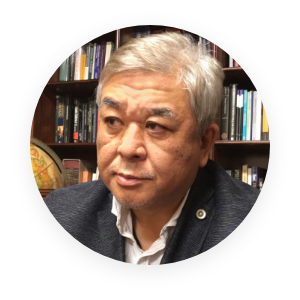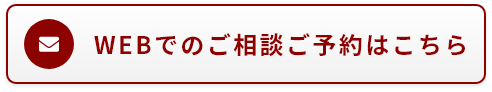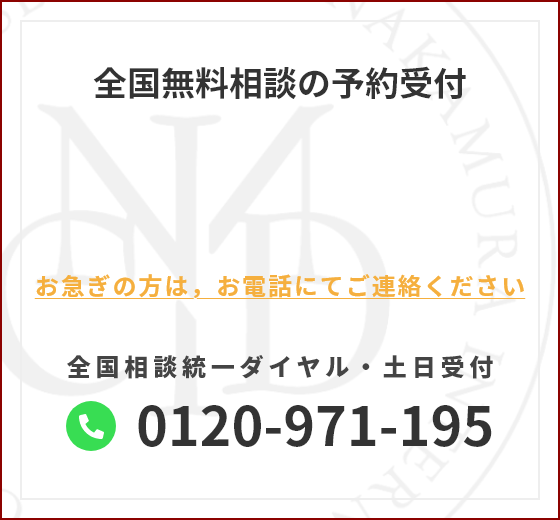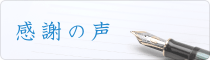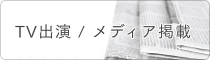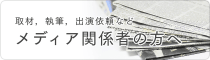勾留延長で社会復帰支援 検察が試行、高齢者らの再犯予防
今日は,「勾留延長と再犯予防」に関する記事です。
窃盗など軽微な犯罪を繰り返す高齢者や障害者らの再犯防止のために、検察が勾留期間を最大10日間延長して住宅確保や就労支援をする取り組みが、全国の少なくとも23の地検で始まっていることが1日、検察当局への取材で分かった。
勾留延長の活用は、容疑者が送検容疑を認めていて、10日間の勾留期限内には支援ができない場合に限定され、本人や弁護人の同意が前提となる。
試行が始まった地検では、取り調べの後に検察事務官が容疑者と面談。老人ホームなどの福祉機関の担当者が同席することもあり、起訴猶予で釈放された場合を想定し、就職先や居住先を確保する。面談での容疑者の姿勢は起訴・不起訴の処分や、裁判で求刑する際の参考にしている。
全国に先駆けて専門チームを発足させた仙台地検では、支援の対象を勾留中に限らず、在宅捜査の容疑者にも拡大。高齢者や知的・精神障害者に対応するため、保護観察所や自治体、NPO法人などと連携し、日常生活や金銭管理の指導、対人関係の改善、親族らへの助言の他、ドメスティックバイオレンス、ストーカー事件では認知行動療法に基づくカウンセリングも実施している。
勾留延長は本来、捜査に時間がかかりやむを得ない場合に限られるため、日弁連幹部の一人は「積極的な再犯防止として評価するが、容疑を認めさせるために利用しないことが大前提だ」と話している。
2014年版の犯罪白書では一般刑法犯の46%超を再犯者が占めた。政府は12年、刑務所の再入所割合を10年間で2割以上減らす目標を設定。再犯者の7割超が無職とのデータ(法務省調べ)もあり、効果的な就労支援が課題となっている。〔共同〕(2014年12月1日11時44分 日本経済新聞)
勾留制度は,「捜査の必要」(罪証隠滅防止と逃亡防止)という,いわば「公共の福祉」のために,「身体の自由」という基本的人権を制約するものです。それは必要最小限のものでなければなりません。当然,身体の自由の拘束期間の延長を認める「勾留延長」という制度も,やむを得ない特別事情がある場合に限って運用すべきものです。つまり、最大48 時間の逮捕期間と10日間の勾留期間だけでは捜査を尽くせない「やむを得ない事由」があるときに認められるのです(刑事訴訟法208条2項前段)。
その「やむを得ない事由」の中には,単に被疑事実の立証に欠かせない証拠が収集しきれていないという事情だけではなく,検察官が起訴不起訴という処分を決定するための諸事情が未だ明らかになっておらず,そのような諸事情について解明する必要がある場合をも含みます。たとえば,当初10日間の勾留中に示談交渉が着手されていて,示談成立見込みですが10日以内には確定できず,10日間延長すればその間に示談成立,告訴取下げが見込めるような場合にはそれで不起訴にできる事情が確定するわけですから,そのような場合にも勾留延長が認められるでしょう。
この点,確かに,「再犯のおそれ」があるか否かについても,検察官の起訴不起訴の判断事情として重要な事情です。しかし,高齢者犯罪者の居住環境や就労環境の不備を直ちに「再犯のおそれ」に結びつけることは,ただでさえ実務上,抽象化され過ぎた「再犯のおそれ」を濫用して保釈阻止等を図っている検察や司法の傾向をさらに助長するものです。本来,高齢者の居住や就労の問題は行政の問題であり,それを身柄拘束という人権侵害を伴う刑事司法制度の利用をもって解決を図るというのは誤っています。行政の怠慢を刑事司法制度の「やむを得ない事由」の中に解消することは原理的には出来ません。身柄拘束制度もその期間を含め,捜査の必要と人権保障のバランスの中でシステムデザインされていることを忘れてはなりません。
生活が苦しいために犯罪を繰り返してしまう人や,精神的な病気のために犯罪を繰り返してしまう人に対し,支援をする必要は高いといえます。しかし,それはあくまでも行政(行刑)の問題でありまして,たとえば,刑務所の出所者を対象に実施されている更生保護制度等を起訴前の段階にも導入し,検察官はあくまでも10日間で捜査を尽くして処分保留として釈放し,その際,更生保護施設に入所できるような制度を設け,同所における生活環境の整備状況や就労機会の確保状況を踏まえて,検察官が最終的に不起訴という処分をするというのが本来の姿です。それを勾留制度で代用するのは間違っているうえ,代用監獄制度を益々定着させるものとなるでしょう。
今回の検察庁の試みに対し好意的に報道する新聞記事を見ると,「身柄拘束」という不利益,身体の自由の制限という問題に対して全く鈍感である我が国の悪弊を見る思いです。「ホームレスにしておくよりも牢屋にぶち込んでおいた方がまし」という感覚がないでしょうか。留置場は「福祉施設」ではなく,「刑事施設」です。
なお,今回の検察の試みでは、被疑者本人や弁護士の同意を条件に運用しているようですが、高齢被疑者本人は,一日でも早く留置場を出たいという方が多いでしょう。もしそのような高齢者が上記のような「勾留延長」に同意するとしたら,「逆らって起訴されたくない」という動機あってのことかもしれません。「同意」を人権侵害の免罪符にしている捜査実務を知る刑事弁護士としては,そのように感じます。国家機関に対する「同意」を人権制限の正当化根拠にしてはなりません。「同意」で逮捕できないはずです。「同意」で家宅捜索もできないと犯罪捜査規範には書いてます。国家機関に対する「同意」は実は真の「同意」ではないということを人類の知恵が示しているのです。
先進国では,我が国の身柄拘束期間の長さは非常識に映っています。この試みも間違いなく,奇異に映るでしょう。
(中村)